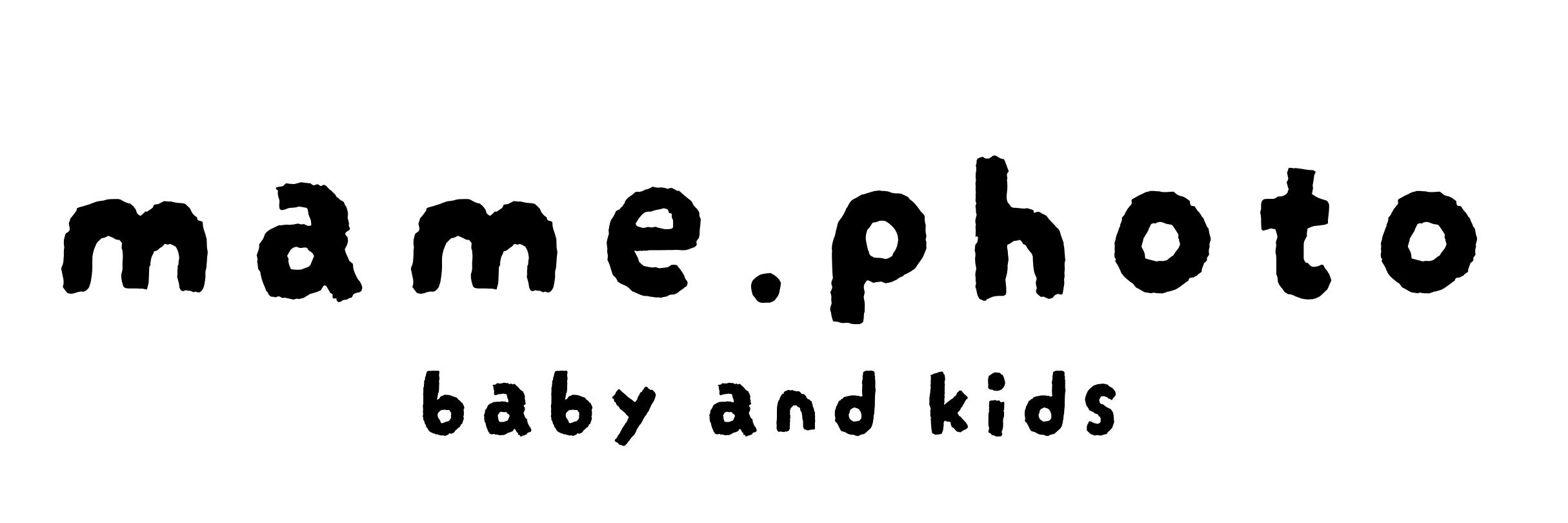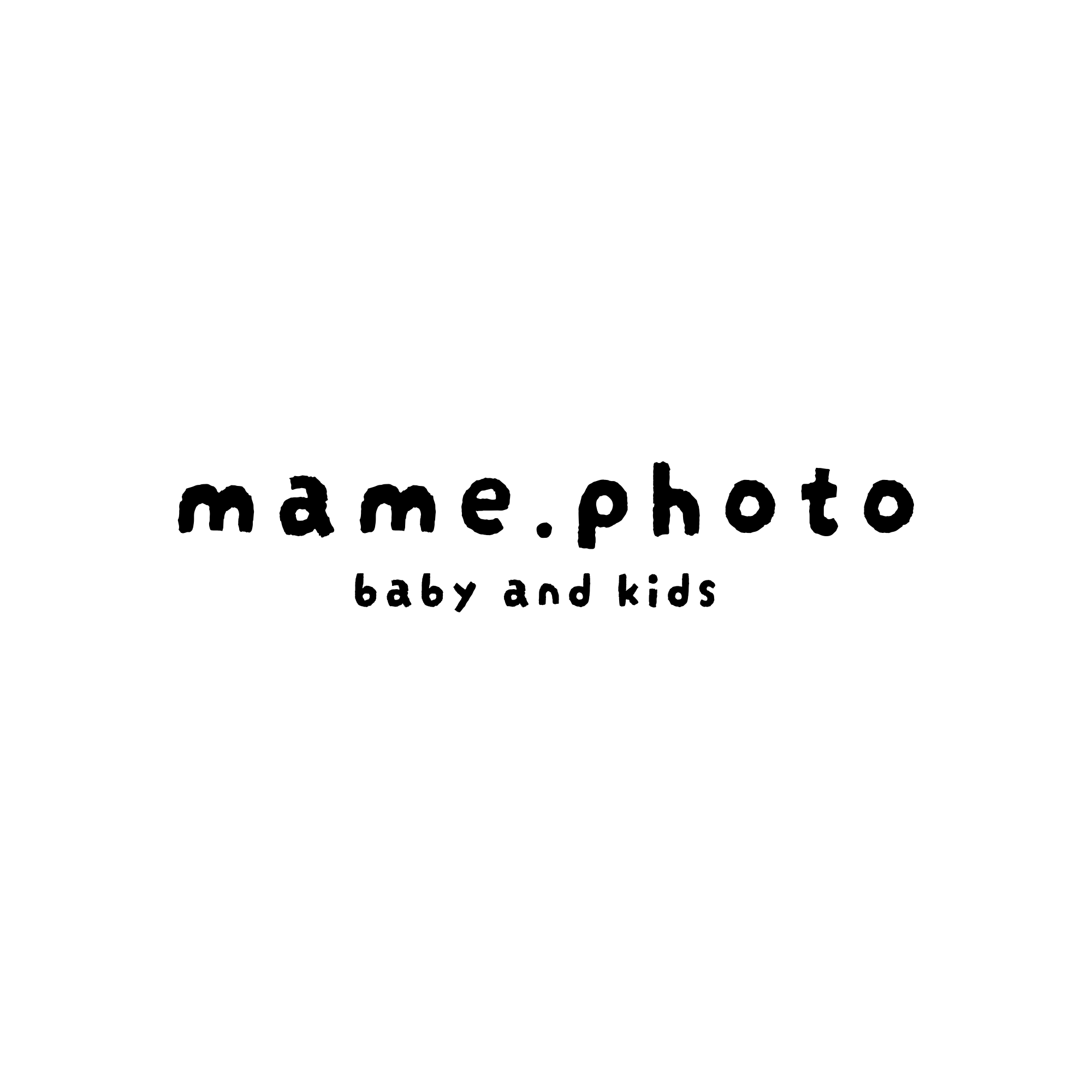原宿で、息子がはじめましての大人たちにたくさん遊んでもらった日。私は、ちょっと前のことを思い出してた。
家庭でも学校でもない「もう一つの家族」
鳥取で暮らしていたころ。移住者たちが集まる、ちょっと風変わりなコミュニティにいたときのこと。
そこには、いろんな価値観や文化的背景を持ったおもしろい大人たちがたくさんいて、子どもたちもその中で自由に過ごしていた。
親じゃなくても、先生じゃなくても、その場にいた誰かがふと子どもと関わってくれて、一緒に笑ったり、ごはんを食べたり、全力で遊んだり……。
大人にとっても、子どもにとっても「家庭でも学校でもない、もう一つの家族」
そんな場所だった。
世界を旅しなくても「子どもの世界」は広がる

この場所にいると、一気に世界を旅することはできなくても、身近な場所にいろんな人がいるだけで、子どもたちの“世界”って、ぐんと広がっていくんだなぁって、すごくすごく実感できたんだ。
よく、「子どもにはいろんな経験をさせてあげたい」って言葉を聞く。
わたしもそう思う。
でも今日、息子がいろんな大人の人と遊んでもらっている姿を見て、改めて感じた。
子どもたちに本当に必要な経験って、出会いからはじまるんじゃないかなって。
いろんな大人と出会って、知らなかった考え方や価値観や生き方に触れて、心がふっと動く。
「やってみたい」
「なんだろう、これ」
そんな小さな芽が生まれる。
そしてそれに親が気づいて、少しずつ一緒に深めていく。たぶんだけど、子どもたちの興味ってそうやって育っていくんじゃないだろうか。
出会いが興味の種になる

わたしがいろんな場所に息子を連れていくのも、無意識に、そんな“出会いのある場所”を求めているからかもしれない。
いろんな文化的背景を持った人たちがいる場所。固定概念がまだないまっさらな幼少期から“ちがい”に出会えるって、すごく意味のあることだと思うの。
「同じ人なんていない」そんな実感を自然と持てることが、きっと偏見や差別から子どもをたちを遠ざけてくれるんじゃないかなって思うんだよね。
「やさしさ」は出会いと想像から生まれる

「誰かにやさしくする」って、 自分と違う価値観に寄り添うことでもある。
わからなくても、想像してみること。
駅前で有名な政治家が演説していた。たくさんの人が集まって、警察やSPもいて、街全体がピリッと張りつめた空気に包まれてる中……
その横で、私は重いベビーカーを一人で持ち上げてバスに乗せた。
まわりにたくさん人がいたのに、誰も手を貸そうとはしない。
「こんなに人がいるのに、必死で子育てしてる人を誰も見てないんだな」
そんな感覚が残った。
誰が悪いとかではない。 でも、政治家の熱量、守る人々の真剣な表情、耳を傾けるたくさんの人たち、そしてその隣で誰にも気づかれない育児のリアルな一場面。
そのギャップが、自分の中ではすごく象徴的だったんだ。
一体わたしたちは「なに」を守っているんだろう?そんなふうに感じたわたし自身も、まだまだ気づけてないことがたくさんあるんだと思う。
その直前、電車の中で聞いた若い女性のつぶやきも印象的だった。
「なんでみんな子どもに優しくできるんだろう。私は親戚の子でも無理。」
私のベビーカーを睨みながら言ったその言葉に、悲しさと同時に、 「きっと、いろんな人と出会う機会が少なかったのかもしれないな。そうだったら、やさしくなるって難しいよね。」と思った。
誰かにやさしくするためには、 自分が満たされていること。
そして、相手の立場を“想像する力”が必要なんだと思ってる。
でもその想像力って、いろんな人と出会う中で育まれていくもの。
私が思う「優しさがある社会」は、ちがいを受け入れられる社会。
誰かの小さなSOSに気づける社会。
どんな人も孤立しない社会。
そしてそれは、未来の子どもたちが、安心して自分の人生を選び、育っていける土壌になるって思うんだ。
自分とはちがう人がいることが当たり前で、 こわがらずに「そうなんだね」って受けとめられる。
ちがうなって思う人を攻撃したり傷つけたりする人がいなくならないのは、きっとそのちがいが「怖い」からなんだよね。
困っている人がいたら「大丈夫?」って自然と声をかけられる。
自分が困ったときも、「誰かに頼っていいんだ」って思える。
そんなふうにして、 子どもたちには“他者とつながる力”や“自分を信じる力”を育てていってほしいと願わずにはいられないんだ。
東久留米にもあたたかい「交差点」のような場所を

だからね、思ったの。
東久留米にも、いろんな大人たちと子どもたちが出会える、あたたかい交差点のような場所がもっとあったらいいなって。
ここには、子育てにやさしい雰囲気もあるし、人と人とのつながりもある。でも、もしそこに“ちがい”が混ざる場所があったなら。
全国から「行ってみたい」って思えるような、価値観がまざり合って、出会いが生まれるような空間。
子どもにとってはもちろん、ママやパパにとっても、世界がひらけるきっかけになると思うんだ。
価値観や考え方って、環境や人との出会いの中で、自然とかたちづくられていくもの。
でも、自分の周りに似たような価値観しかなければ、気づかないうちに世界はどんどん小さくなってしまう。
だからこそ、いろんな価値観が混ざり合うような、あたたかい“交差点”みたいな場所が、もっと身近にあったらいいなって思う。
まめフォトも、そんな場所が育っていくきっかけになれたらな。ただのフォトスタジオじゃなくて、親子が世界とつながる“出会いの入り口”になっていけたらいいな。
興味は親が「気づく」もの

子どもたちの興味は、親が育てるものではないのかなって思ってる。
親ができることは、子どもが誰かと出会い、世界にふれて、心がふっと動いたときに、そのサインにそっと気づいてあげること。
そこから、少しずつ一緒に深めていく。
わたしはそう思うから、「経験の場」と同時に、「出会える場所」も大切にしたい。
ママの世界が広がると、子どもの世界も広がる

そしてね。やっぱり思うの。
子どもの世界を広げていくためには、まずは、ママの世界が少しずつ広がっていくことも、大事なのかもしれないなって。
ちょっとだけ厳しく聞こえてしまうかもしれないけど……ママ自身が、自分の世界に閉じこもっていたら、どんなに子どもの可能性を信じていても、届けられる景色には限りが出てきてしまうこともあるのかなって思う。
でもね、それってなにも大きなことをしなきゃいけないってことじゃなくて。
新しい人と出会ったり、ちょっといつもと違う場所に行ってみたり、ふとした瞬間に「これ、いいかも」って心が動くことを大切にすること。
そんな小さな経験の積み重ねが、子どもに見せてあげられる未来にも、やさしく広がりをくれる気がする。
もちろん、それぞれの心地よさや幸せの形があるから、この考えがすべてだとは思わない。
でも、もし今、「もっと世界を広げてみたいな」って感じているママがいたら。
「子どもに、いろんな出会いを届けてあげたいな」って思っているママがいたら。
私はそんなあなたと、一緒に歩いていけたら嬉しいなって思ってる。
子どもたちが、自分の世界を見つけていく最初のきっかけが、あたたかくて、やさしい“出会い”でありますように。